ルビコンのPMLCAPを選択すると艶っぽくなり抜けも上々です
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
という書き込みをXで見かけたが、自分の感じ方と正反対で思わず苦笑いであった。
書き込んでいる方は基板頒布で有名?な方なので うーーーん...
自分が今までやっている事がすべて否定されてる感じで(笑)
自分のルビコンPMLCAPの印象はとにかく音が減る(静かになるが)という印象なんですよ(笑)
とても説明がつかない理解不能で混乱している。
参考URL
0.1μFのパスコンを200個以上購入して交換した話
電源基板へ音質調整のため追加や交換しているコンデンサーの類








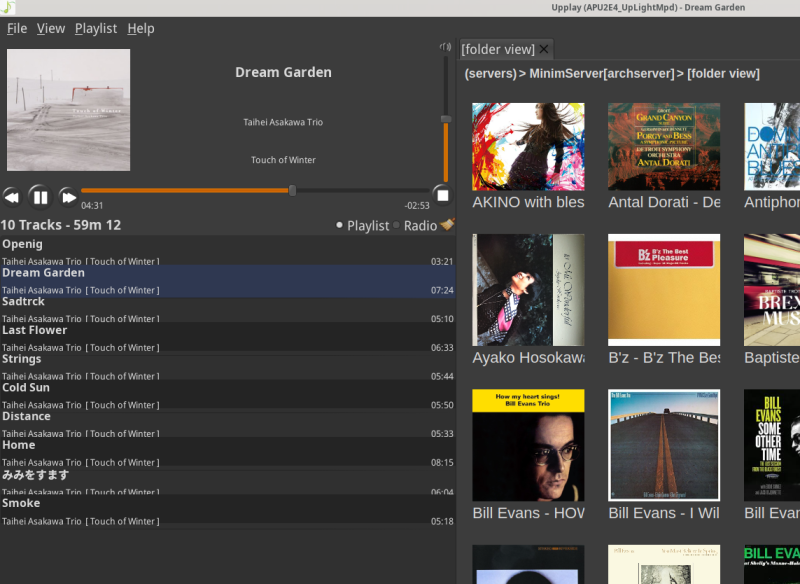




Comments