薄膜高分子積層コンデンサー(PMLCAP)10μF25Vを
初段の可変三端子リップルフィルターへ付けて見たくなって
熊電源12.0V出力のケースを開けたら(DirettaホストのAPU2D4に使用)
大型タンタルコンデンサーが液漏れをしていた。
上部防爆弁付近だったので幸い基板パターンには付着していなかった。
あらら良い感じだったのに残念...
同型予備もあるが大事を取って日本製の通常品へ交換(笑)
リップルフィルターへ取り付けて見た結果としては今までのPanasonic製と比較して
更に音が太く感じられて成功だと思う。
同じ型の電源基板が嫁入りしている方々に
声をかけないとダメかなぁ...
参考リンク 業務連絡(1)









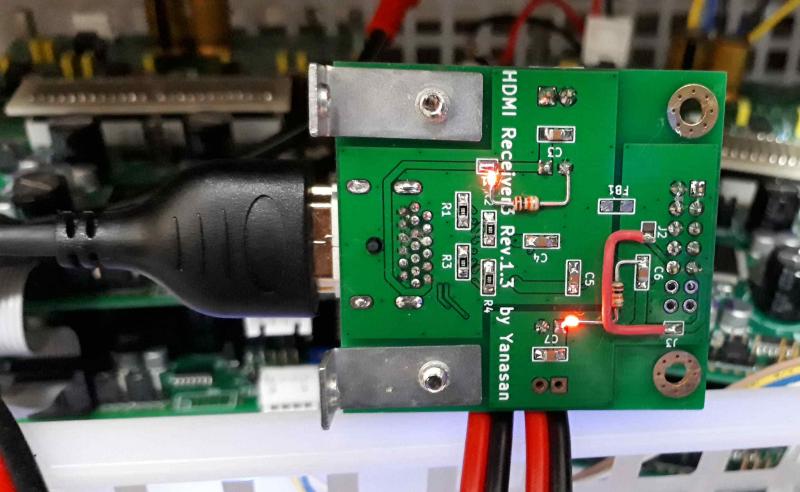
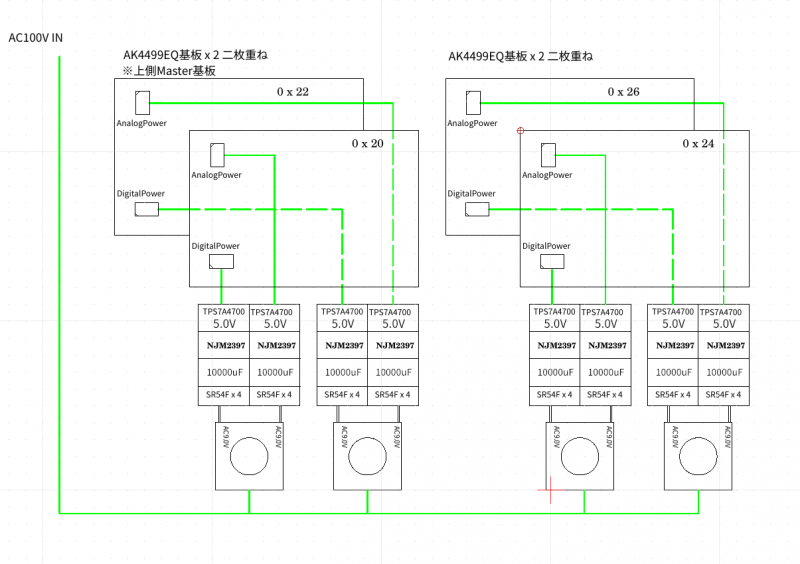
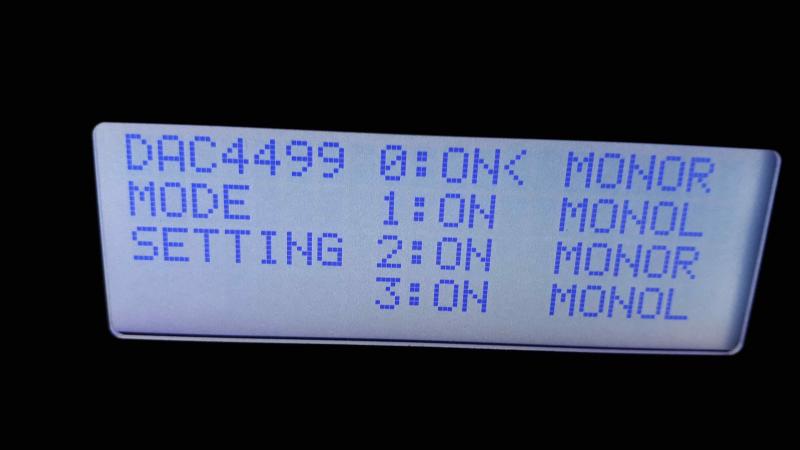

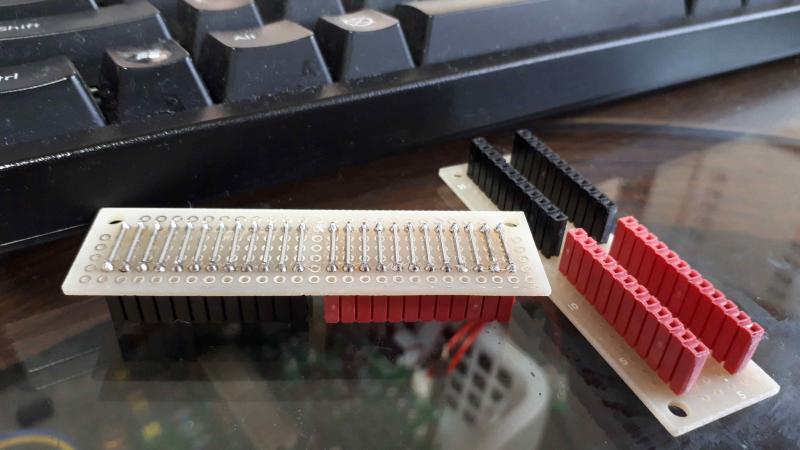

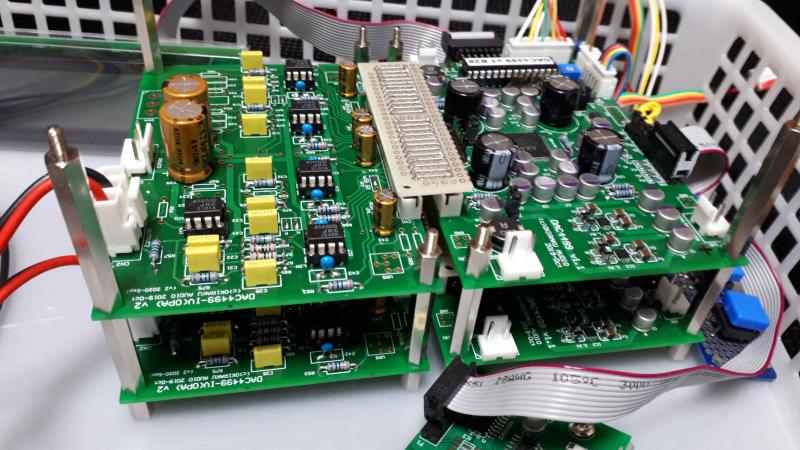





Comments